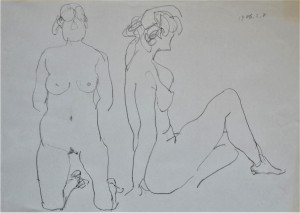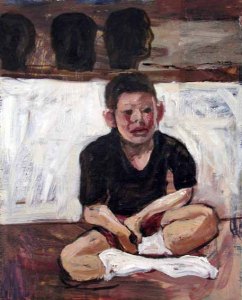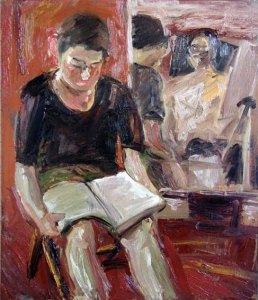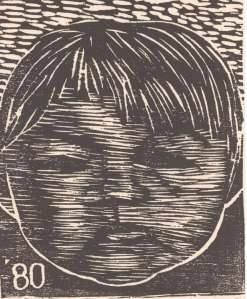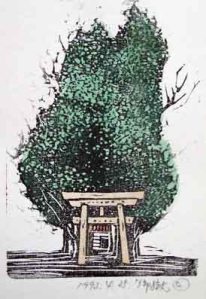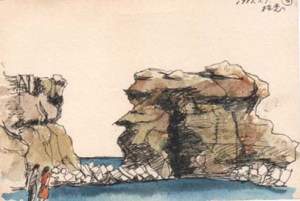国立民族学博物館が、人類の移動を全地球規模で考える共同研究に取り組んで、今年は最終年の5年目に当たる。「人類の移動誌――進化的視点から」と名付けたこの共同研究に参加しているメンバーを中心に、13人の研究者が分担・共同執筆した。
テーマごと執筆者が異なる場合、ある部分はやけに専門的だったり、逆にぽっかり抜け落ちる部分があったりして、しばしば全体像が分かりづらくなる傾向がある。この本は700万年前にアフリカで人類が誕生してから、進化を重ねて20種以上の人類に枝分かれし、現生人類(新人、ホモ・サピエンス)だけが全地球上に広がった様子を、要領よく明らかにしている。コーディネートの勝利であろう。
「出アフリカ」の謎の解明、アメリカ大陸やオセアニアへの移動、ネアンデルタールと新人の関係、縄文人と弥生人の出会い、類人猿の観察から考えられた人類社会の進化・・・などが、コンパクトにまとめられている。人類進化と移動に少しでも関心のある読者には、格好の入門書。やさしい記述で素人にも分かりやすい。
一般教養書的ではあるけれど、内容は最新の知見が盛り込まれている。新人にネアンデルタールのDNAがかすかに混ざっている、とするニュースが昨年流れ、私は眉唾かなと思っていたが、これは本当のことらしい。
ネアンデルタールと同じ旧人に属すると考えられる、シベリアで見つかった「デニソワ人」が、新人と混血してサフル人(オーストラリア原住民、パプアニューギニア高地人など)になった。それ以前にサフル人から分離した、アンダマン諸島やフィリピンのネグリトは、デニソワ人とは混血しなかった、など最新のDNA研究がもたらした成果は目を見張るものがある。
私個人は、DNA分析に代表される「科学的」研究が、本当に正しいのか、一抹の不安を持っている。科学や統計処理には、たいてい仮説あるいは前提があり、かつ誤差を伴う。全面的ではないにしろ、部分的に覆ったり、訂正を迫られる時代が来ることはないのだろうか?
ともかく、私の「人類の足跡を訪ねる」放浪に格好のガイド・ブックが現れた。ちなみに、この本の中に私の撮った写真も1枚使われている。私の無益な貧乏旅行も少しは役に立ったようで、ちょっとウレシイ。みなさ~ん(レナ・ジュンタの口調で)、買ってあげてくださいね~。1、400円、朝日新聞出版。