ルワンダでは1960年以降、多数派フツによる少数派ツチへの虐殺が、繰り返し起きていた。その殺戮は「ムヤガ(風)」と呼ばれた。ツチに生まれた著者のセバレンジも、幼少のころ隣人フツに匿われて難を逃れた。繰り返されるムヤガを案じた父の計らいで、著者は隣国コンゴ民主共和国の小学校に転校、同地で大学を卒業し、同じツチ難民の女性と結婚したのち母国に戻った。
1994年、犠牲者100万人とも言われるジェノサイドが勃発した。セバレンジ家族は危うく難を逃れてブルンジへ、さらにカナダへと亡命したが、父母をはじめきょうだいや親類縁者の大半が殺された。
ジェノサイドは、ツチ難民らを中心に組織された、反政府勢力ルワンダ愛国戦線(RPF)の勝利で終結。セバレンジはルワンダに戻って国会議員になり、若くして議長にまで選らばれた。
この本のピークは2つある。1つ目は、このフツによるジェノサイド。2つ目は、実権を握ったRPF指導者のカガメ(当時は副大統領で軍を掌握、のちに大統領)の独裁化と、彼と対立した要人たちの亡命である。後者に著者も含まれ、現在は米国の大学で教鞭をとったり、人権活動に従事している。
この本を読むと、ルワンダのジェノサイドが、多数派フツが少数派ツチを殺した、とする単純な構造ではないことがわかる。
簡単に歴史的経過を並べると――かつてこの地にはツチの君主国があった。その構成はツチ、フツ、トゥワ(原住民ピグミー)の3者で、互いに平和に暮らしていた。19世紀末、アフリカが西欧列強の間で勝手に分割統治されることになり、ルワンダは最初にドイツ、のちにベルギーの植民地となった。ベルギーがとった植民地統治は、ツチ優先の民族分断政策だった。このときフツは政府の要職から追放され、教育の機会も奪われた。ここに民族差別・ジェノサイドの種がまかれた。
大戦後、アジア・アフリカで独立の機運が高まり、ルワンダでもツチを中心に独立運動が盛り上がると、ベルギー政府は、それまでの政策を一転させ、ツチから権力を奪い、「正義の名の下に」フツに権力を与えた。ツチの受難の始まりだった。
また、ジェノサイド後のルワンダについて、民族の和解が進み、国際社会から「安定と経済発展のモデル」として好意的に紹介されることが多いが、その実、カガメの独裁化が進行した。カガメの意向に沿わなかった政府や軍、メディア、非営利団体の重要人物が次々と国外に亡命している。前大統領も投獄され、さらに暗殺が疑われる不審な死を迎えた要人もいる。また、著者によると、刑務所には劣悪な環境下でたくさんのフツが現在も収容されており、十万人単位のフツ難民も国外に逃れている。ツチによるフツ虐待もあったのだが、無視されてきた。
このままでは、またいつか、同じような対立、迫害が起きかねない――著者の危惧が杞憂に終わるのかどうか?
♪
繰り返されたジェノサイドの中で、ツチ家族が隣のフツ家族に匿われて助かった、などの“美談”も伝えられる一方で、次のムヤガでは、その同じフツ家族に殺害されたケースもある。著者の家族もそうだった。RPFと政府が衝突すると、フツの中に自警団が生まれ、報復のように一般のツチが犠牲になった。隣のツチを匿ったフツが、その足で自警団に加わり、ツチ殺しや家屋の焼き払いを行った。フツにとってムヤガに参加することは、国民の義務と同様だった。(これって、戦争の論理とおんなじだなあ。それと、百年前の関東大震災のときの朝鮮人・中国人虐殺でも似たような出来事があった。)
♪
ルワンダのジェノサイドについては、「悪いフツ」「和解と経済復興を遂げたツチ」のイメージで報じられてきた。脱線するけど、ある人気ジャーナリストが、データベースやネット検索から集めて来たような、ルワンダ・ジェノサイドのハナシを、さも物知りのようにとくとくと解説するのを目にしたことがあるけれど、本当のところは、もっと複雑で根が深い。そーいや、このジャーナリスト、カンボジアのポルポト派によるジェノサイドについても、ポルポトを排除したヘン・サムリン政権の意を反映した、虐殺記念館の言い分をそのまんま、しゃべっていたなあ・・・ヘン・サムリンも世襲制独裁になっちゃってるみたいだし・・・
正義も不正義も、実際には紙一重の感あり。











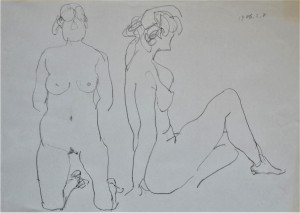





















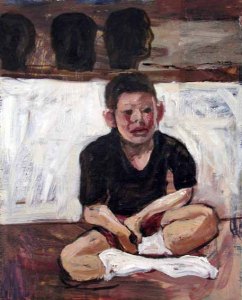


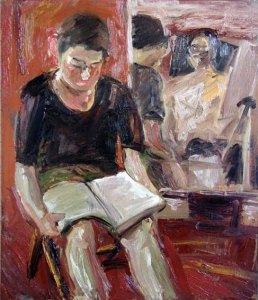



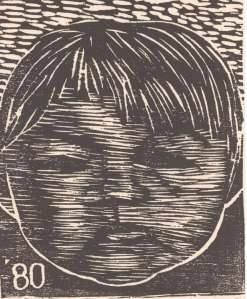


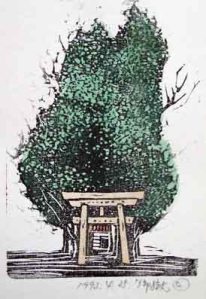









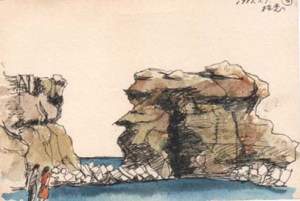






















コメントを残す