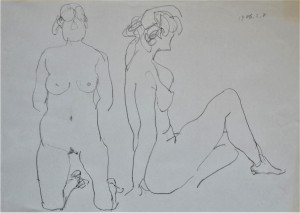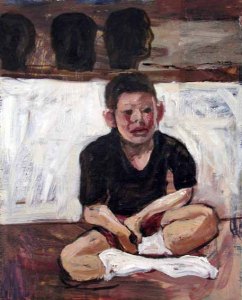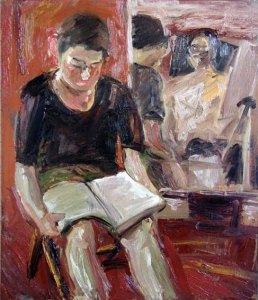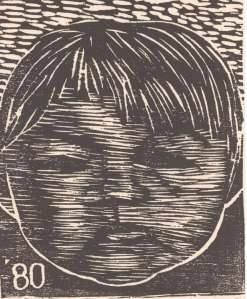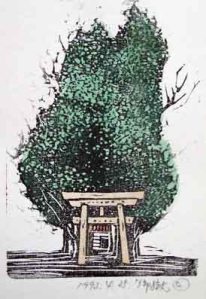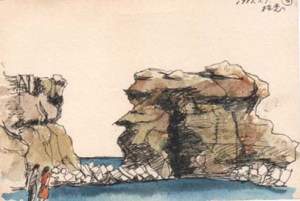この本は何度読んだことやら。現代漫画といったって、1969年刊、つまり半世紀以上も前に刊行されたもの。戦後日本漫画界の大御所を集めたシリーズ全15巻の1巻。私が持っているのは、古本屋で求めたこの1巻のみ。最近、たまたまテレビ・チャンネルをガチャガチャさせていたら、園山俊二の「国境の二人」を取り上げた番組に遭遇した。残念ながら番組全体は見ていない。
園山俊二という漫画家には特別な思い入れがある。
小中学生のころ、漫画家になりたいなあ、とぼんやり憧れていた時期があった。毎日小学生新聞に連載されていた、園山俊二の「がんばれゴンベ」を読んで以来の夢だった。「がんばれゴンベ」は、作者が早大在学中の1958年から亡くなる前年まで、35年間にわたって計9775回連載されたそうだ。私が読んだのは、最初の半年間~1年間分くらい。当時、小学3年生くらいだった。
連載はそこでいったん完結したはずだった。作者の都合で連載を終了するとの挨拶と、お山に帰るゴンベが列車の窓から読者に向かって「さよなら」するシーンは、ずっと記憶に残っていた。それほど間を置かずに連載が再開されたことは後で知ったが、わが家では小学生新聞をとってくれなくなったので、その後のゴンベを読んだのは、ずっと後になってからだった。
その後ずーっと経った1984年か1985年に、作者本人にお目にかかったことがある。私(ピカテン)が雑誌記者をしていたころで、作者はその雑誌に月1の連載をしていた。その連載が急に休載になった。作者の病気治療のためだった。編集部としてお見舞いに行くことになり、私は真っ先に手を挙げた。夕張メロンを手土産に、東京の病院に向かい、入院中の作者を見舞った。
ベッドから起き上がった作者は、一見お元気そうだった。予想通りの、優しい柔和な表情で迎えてくれた。私が「小さいころから先生のファンでした。がんばれゴンベをいつも楽しみにしてました」というと、ちょっと照れくさそうにしていたのが印象に残った。シャイな人だった。
園山俊二は1935年4月23日生まれ、1993年1月20日没。生きていれば今年で米寿、没後30年の節目に当たる。
この本のあとがきと別刷りに園山自身と早大漫研の仲間だった東海林さだおが、それぞれに文章を寄せているが、ふたりとも自由な発想と天真爛漫さで、実に面白い。
残念ながら、この本には「がんばれゴンベ」は収録されていない。で、手元にある別の「がんばれゴンベ」シリーズ3冊にも目を通す。 このところ、ちょっと小難しい本や医学関係の文章を読むことが続いていたので、もともと硬いアタマが、さらにこり固まっていた。園山俊二、東海林さだお、それにゴンベやギャートルズの柔軟にして強靭な思考(これぞレジリエンス!)で、少しはもみほぐされた感じがした。