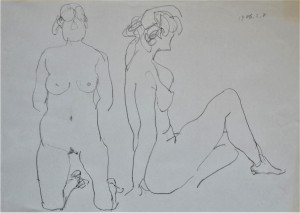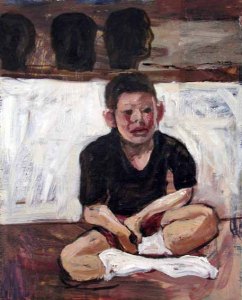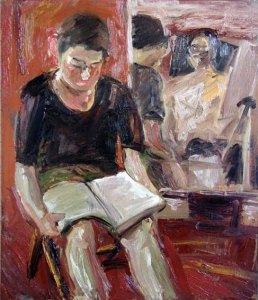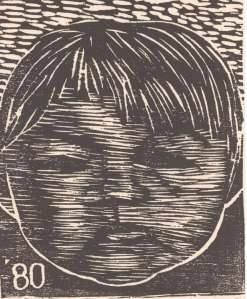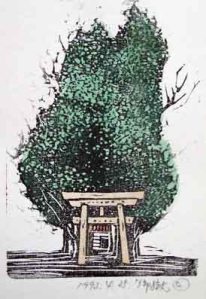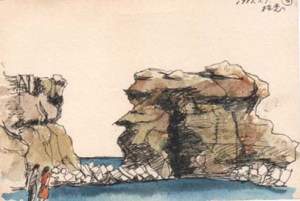われわれヒト(ホモ・サピエンス)は、他の生き物からかけ離れた特別な存在である。際立っているのは、直立二足歩行、大きな脳、道具製作・使用に代表される文化を育んだこと、など。この3つは密接に関係している。
鳥や恐竜・爬虫類の一部に二足歩行する生き物はいる(いた)が、直立二足歩行する生物は他にいない。過去にもいなかった。空を飛ぶ、という極めて特殊で難しい技は、昆虫、鳥(翼竜)、コウモリ(哺乳類)で別々に進化したというのに、直立二足歩行という技は、人類以外は選択しなかった。直立二足歩行は、足が遅く、腰などに負担がかかり、四足歩行に比べてかなり不利なのだ。
人類はなぜこんな不利な方法を選んだのだろう?
著者はこれまでに提唱されている様々な仮説を検証する。ちょっと前まで、教科書にまで書かれていた「イースト・サイド・ストリー」は次のようなものだった。
800万年前、東アフリカ大地溝帯の活動で南北に連なる大山脈が造られた。偏西風が運んできた水蒸気は山脈で遮られ、東側は乾燥化した。樹木のまばらになった東側にいた人類の祖先は、草原に出て直立二足歩行を始めた————
のちに山脈西側でサヘラントロプス化石(直立二足歩行の初期猿人)が見つかったことなどから、この説が誤りだったことは明らか。
「人類は直立二足歩行を始めたことで手がフリーになり、石器などの道具を制作したので脳が大きくなった」とする説も厳密には正しくない。「人類は直立二足歩行を始めてから450万年もの間、石器も作らなかったし、脳も大きくならなかった」
人類が直立二足歩行を始めて、これまでの700万年間に25種くらいの異なった人類が誕生し、われわれ以外は絶滅した。ネアンデルタール(脳容積1550cc)、ハイデルベルゲンシス(1250cc)、エレクトス(1000cc、以上はホモ属)、ドマニシ原人(600cc、エレクトスとアウストラロピテクスの中間種?)、アウストラロピテクス(450cc)・・・。
ヒト(ホモ・サピエンス、脳容積1350cc)と、人類に一番近いチンパンジー(390cc)を比べると、脳の大きさは段違いである。ヒトが他の生き物の中で他とは隔絶した特別な存在であるようにみえるのは、途中の彼らが絶滅してしまったからだ。
「脳の増大はそろそろ終わりかもしれない。ネアンデルタール人は私たちより脳が大きかったし、昔のホモ・サピエンスも今の私たちより脳が大きかった。数万年前が脳の大きさのピークで、今は下り坂に差し掛かったところのようにも思える」。
直立二足歩行は長距離移動に向いている。以前、私=ピカテンは「長距離を歩く必要がなくなったヒトは、将来四足歩行に戻る=進化するのではないか」と戯れ言を書いたことがある。脳が小さくなってきているかもしれない、とはついぞ想像もしていなかった。「使わなくなった有料アプリを少し整理している時期」かもしれない、のだそうだ。私自身はここ10年間くらい、脳のアプリを削減し続けているような気がする(関係ないか?笑)。