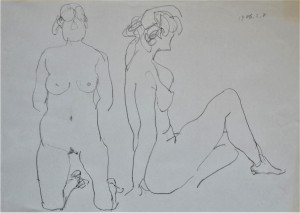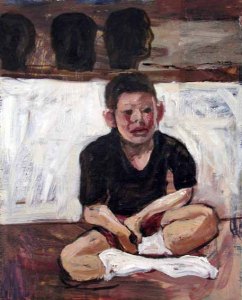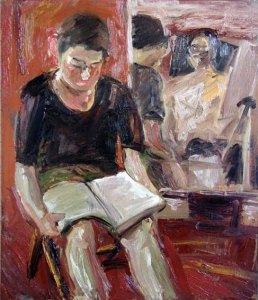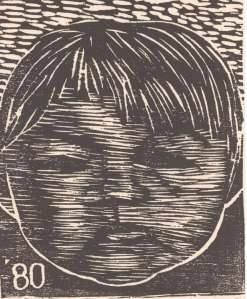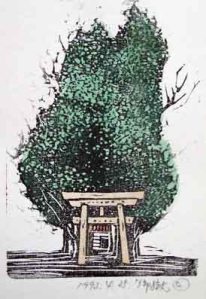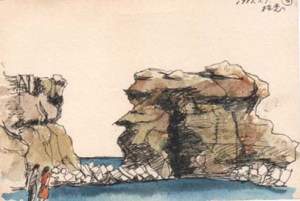先の大戦中、昭和18年ころから日本と独伊間の連絡は、無線通信のみになっていた。共同作戦を遂行するための人的交流や兵器技術・軍需物資の交換が必要とされても、連合国側に制空権を奪われ、飛行機や船舶による連絡は不可能だった。
そこで考え出されたのが、潜水艦による独訪問作戦だった。敗戦までに任務についたのは、日本の第1級潜水艦「伊三十」「伊八」「伊三十五」「伊二十九」「伊五十二」。片道2ヵ月を超える隠密行動は困難を極め、日独間を往復して日本に戻れた艦は1艦だけだった。他の4艦と多くの潜水艦乗りが深い海底に沈んだ。
その戦史を、作者は克明な文書記録に加え、数少ない生き残りや多数の関係者の証言を得て、克明に描ききった。史料と証言の隙間を、作家の想像力で埋めたような「半ばフィクション」のノンフィクションが多い中で、著者はあくまで事実に徹する姿勢を貫いている。
時には乗組員の名前の羅列が、煩わしく感じたりもするけれど、いくつもの秘話や苦闘ぶりがリアルに描き出されていて、長編ながら最後まで飽きさせない。
♪
在独日本大使館と本国の間の暗号無線は、連合国側によって逐一傍受され解読されていた。盗聴されても意味が分からないようにと鹿児島弁でやりとりした、エピソードも興味深い。それを解読した米陸軍情報部に、父が鹿児島出身でサンフランシスコ生まれの米国籍を持つ伊丹明がいた。彼も、戦争に翻弄された人生だった。
中学、大学と父の故郷・鹿児島で国粋主義的な教育を受けた彼は、開戦前に両親のいる米国に戻っていて米軍に召集された。鹿児島弁をよく理解できた伊丹は、日本側で交わされた鹿児島弁を正確に英訳した。日米両国への忠誠と裏切り、個人の思想にかかわらず故郷や恩人を裏切る結果になった彼の行動。戦後、苦悩した伊丹は奔放な生活の果て、タクシー内でピストル自殺をして自らの生涯を閉じた。
♪
昭和18年4月26日、インドの反英独立活動家チャンドラ・ボース(当時ドイツに滞在していた)を乗せた独Uボートと「伊二十九」がインド洋で極秘裏に会合し、ボースたちが移乗に成功した様子もこの本に書かれている。
ボースは11月に東京で開かれた「大東亜会議」に姿を現し、12月には、インド領のアンダマン諸島に3日間だけ赴き、自由インド独立の旗を掲げた。このことは、拙書「古人類趾巡礼」の第6章「ネグリトに出会う(インド・アンダマン諸島編)」でも触れた(蛇足ながら)。