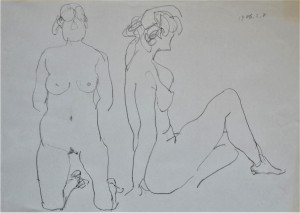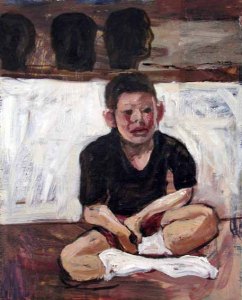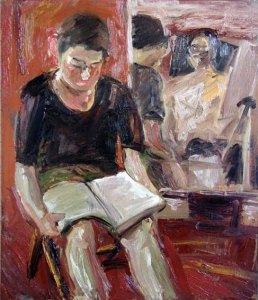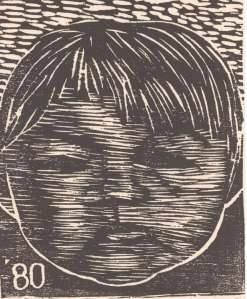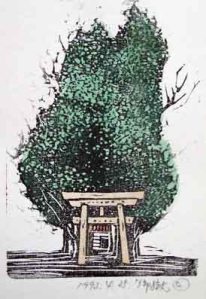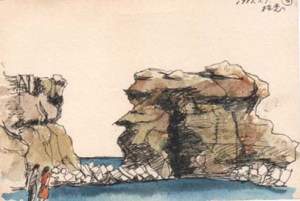トンガなど南太平洋の人々は、なぜあのようにデカく屈強なのだろう。欧米流の食生活が入ってきた近年になって現れた特徴ではない。クック船長らこの地にはじめて足を踏み入れた西欧の探検家・船乗りたちも同じような記述を残している。
これまでのさまざまな研究は、大柄で筋肉質の人間ほど、この太平洋を島伝いに移動することが可能だったことを示唆する。赤道付近とはいえ、小さな船や筏でこの海を移動するのは、体温を維持するのが困難だった。
体熱産生・発散の関係で有利な大柄な人間だけが、この困難を克服できたのだろう。
著者はニュージーランド・オタゴ大学で太平洋の人骨資料を研究した形質人類学者。この本はその研究の集大成といった内容。他の研究者たちや過去の研究成果にもまんべんなく目配りしている。
南太平洋への人類進出のプロセスは、まだまだ謎が多い。頭蓋骨やDNAのデータから多変量解析やらクラスター分析やらといった数学的手法で人種系統を論じたり、言語学の方からのアプローチもある。
これらは南太平洋の島々の人々は、アジア側から移住した人類の子孫であることを明らかにしたものの、そのルートや時期、規模など、ディテールとなると議論の余地が大きいらしい。クラスター分析の中には、日本人の隣にニュージーランド人(ネイティブ)が来るような、常識から考えてもヘンな報告もある。
さまざまな研究に言及し、専門的な知見を加えている分、素人には読み通すのが少ししんどい。「クック船長の見た人々」と、原題にはないと思われる副題を付けたのはさすが。片山一道訳。装丁も美しい。
168ページの図4-11の中の「人口変形」は「人工変形」の誤植。