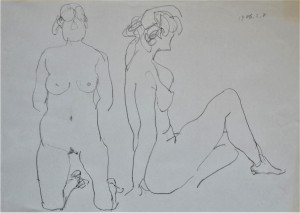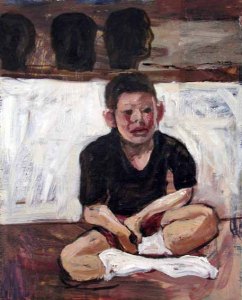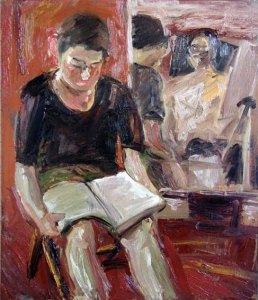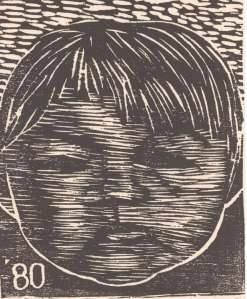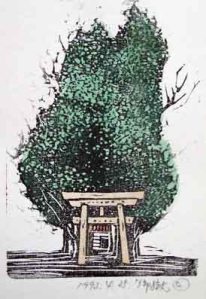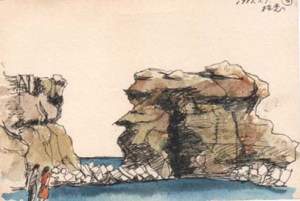全5巻の第1巻。このシリーズは、たしか東大の赤澤教授を中心に今から20年ほど前に行った、プロジェクトの成果をまとめたものだったと記憶する。1995年の刊行当時、2~4巻は読んだのだが、1、5巻を読んでいなかった。
執筆者はこのプロジェクトに参加した全国の人類学者たち。
アジアに起源を持つモンゴロイドは、オセアニアや南北アメリカに渡り、地球の3分の2を占めるまで分布域を広げた。第1巻では、その拡散と移動のありさまやモンゴロイドの特徴を、化石や骨格、遺伝子、古写真から検討している。
当時は人類のアフリカ単一起源説と多地域進化説が、どちらが正しいとも決着がついていなかった時代。遺伝子の解析が始まって単一起源説が優勢になってきていたものの、モンゴロイドは北京原人やジャワ原人の流れを汲むと考える研究者も多かった。
この本もその時代を反映して両論併記になっている。遺伝子の方からはアフリカ単一起源を、化石や骨の形態からは多地域進化が語られる。
例えば今ではすっかり旗色の悪い後者の論。「アジアではほお骨の発達にもとづく顔面の平坦性や高頻度のシャベル形切歯などの特徴は連続しており、アフリカとはまったくちがう。石器制作技法も、東アジア、東南アジアとアフリカ、ヨーロッパとではことなっている」「アジアでは古代型から現代型への進化が独自におこった」等々。
アフリカ単一起源に軍配が上がったかに見える現在からふり返ると、個々の研究は間違いではなくとも、20年の歳月を感じますね~。
モンゴロイドについて思うのは、その旺盛な繁殖力や生命力のすごさである。大海原を超え、極寒を克服し、自らの身体をその土地に合わせて変え・・・人類が地球上のすみずみにまではびこったのは、モンゴロイドのこの高い適応力によるところが大きい。
つい最近になってアメリカ大陸や太平洋の島々にたどり着いた、コーカソイドがこれらの土地を「発見した」なんぞと言うのは、厚顔にもほどがある。もっとも先にたどり着いたからエライってもんでもないか・・・な?