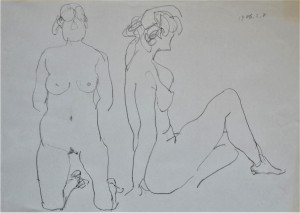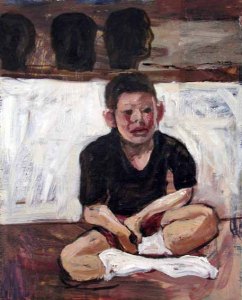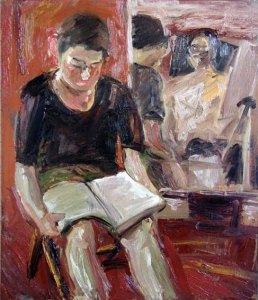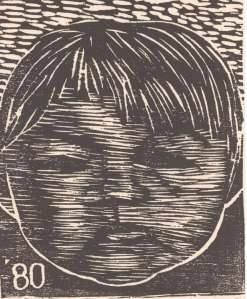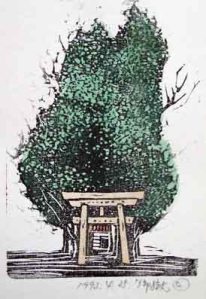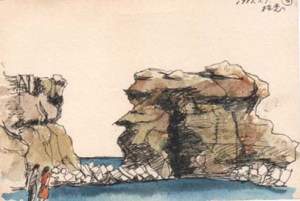1994年から2000年にかけて雑誌「科学」に掲載された「心の進化」にかかわる33本の論文、解説、座談会などを一冊にまとめた。本と雑誌の中間、いわばムックのような体裁。筆者は長谷川寿一、長谷川眞理子、松沢哲郎、澤口俊之、澤口京子、山極寿一、諏訪元、さらには海外からJ・グールドも加わって多士済々たる顔ぶれがそろった。
人類の心の進化を、ヒトの行動はもちろん動物行動学や考古学、さらには最新の脳科学なども取り入れて、多彩に論じている。
ゴリラの観察で名を馳せた山極の「人間社会の由来」の一部を、少し長くなるけどそのまま抜粋すると
「チンパンジーもボノボも劣位な個体が優位な個体に近づいて手を差しだし、食物を乞う行動がみられる。ゴリラでも相手の顔をのぞき込んで採食場の譲渡を迫ることがある。そして、優位な個体はこの要求をなかなか拒むことができない」
「分配は、両者が食物を通して互いのきずなを確かめようとする欲求から発現する社会的な交渉と考えられている。人間の祖先は、この行動に食物を交換材として用いる経済的な意味を付与し、相手に乞われなくても自ら進んで食物を与える積極的な分配行動を発達させた。この過程は、アウストラロピテクスからホモ・ハビリス、ホモ・エレクトスに至る200万~300万年前の間におこったに違いない」
「直立歩行はエネルギー・コストを下げる生物学的な理由から、他方、食物の分配は互いのきずなを確認し仲間に譲歩を迫る社会学的な理由から発達した。おそらく、そこには言語という人間独自のコミュニケーションの発達が不可欠だった」
長谷川眞理子、長谷川寿一の「戦前日本における女子死亡の過剰」も、おもしろい。
男より女の方が長生きする(つまりは、ほぼすべての年齢区分において男の死亡率は女のそれを上回る)のは世界的に共通するが、部族社会ではこれが逆転することがある。差別的な女児殺し、医療や栄養面での男尊女卑が原因と考えられる。
日本でも戦前は同じ逆転現象が見られたが、特に1900~1930年にかけては女の死亡率が著しく高くなった。当時、15~19歳の女子の13%が紡績女工であり、その2.3%が結核で死んだ。「ああ、野麦峠」である。
この女工哀史に代表されるように、富国強兵と近代産業化の下で女子に対するネグレクトが広範囲に蔓延していたことを意味する。
私も女工哀史は知ってはいたけれど、統計に数字となって表れるほど、大がかりなものだったとは!正直なところ驚きだった。