つづけて有吉佐和子の小説。「恍惚の人」は50年以上前の大ベストセラーである。当時読んだ人が多いはずだが、私(=ピカテン)は読んでなかった。会社勤めを始めたばかりで、小説を読むようなゆとりがなかった。でも「恍惚」や「恍惚の人」といった言葉が、当時、流行語のようになっていたことは、よく覚えている。
あらためて読んでみると、面白い。老人介護の問題は50年後の今日、ますます深刻になっているのではないか? 少なくとも老人の絶対数は、当時と比較すると圧倒的に増えている。介護を必要とする老人、徘徊老人の数だって増えているのじゃないだろうか。
この小説も1つの契機となって、その後の介護制度や老人関連施設(公共・民間を問わず)が増えたこと、老々介護やその果ての家族殺人・無理心中・自殺などの事件に社会の関心が向けられたこと、など著者には社会(時代)を読む、先見性があったと言うべきだろう。あとがきに「老人福祉史に記録されるべき」作品とある。その通りだと思う。
小説のメーンテーマは「犠牲になる嫁」で、ボケ徘徊老人を介護する、息子の妻(昭子)の物語なのだろうが、現在、嫁が舅姑の介護をするケースは、どの程度なのだろう? 隣近所や知人を見回すと、娘が実父母と同居する例の方が目に付く。
こちらが男のせいかもしれないが、小説の中で、ボケ老人(茂造)の息子(信利)が「耄碌している父親は、信利がこれから生きて行く人生の行きつく彼方に立っている自分自身の映像なのだ」と思うのには、身につまされる。
信利は50歳くらい? 私=ピカテンは、信利よりも茂造の方に限りなく近い。茂造は「彼方に立っている」のではなくて、「目の前にいる」のである。
♪
私事だが、7年ほど前から続けている高血圧の薬の服用に加え、昨年からは狭心症、さらに右脚の痛みで整形外科通いをしている。さらに狭心症の治療を受けている病院で血管のスクリーニングなる検査を受けたら、脳動脈瘤と脳委縮の疑いを指摘された。
日ごろ、物忘れが多いから「いよいよか」と、半ば覚悟を決めて脳外科専門病院に詳しい検査を受けに行った。結果は————動脈瘤はなし、脳委縮も年相応で問題なし。先日受けた、75歳以上運転免許更新の認知検査もなんなくパスした。やれやれ・・・
ボケ老人・耄碌の烙印は免れたが、アタマもその他の肉体も、そろそろ耐用年数の期限切れに近づいていることを痛感している。











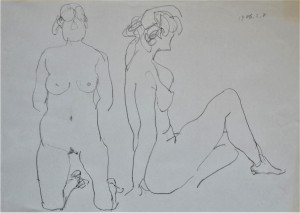





















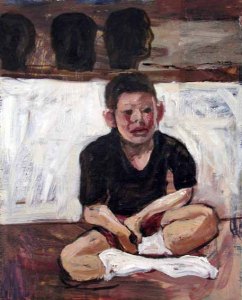


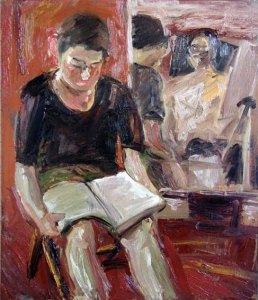



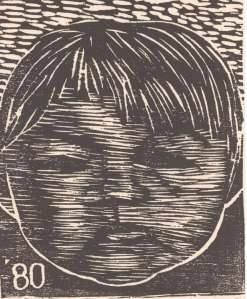


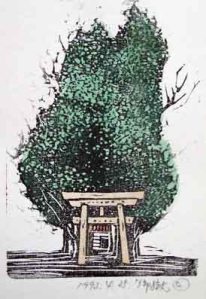









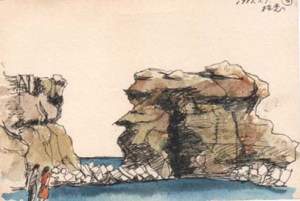






















5月 12, 2024 @ 09:52:32
有吉佐和子の「恍惚の人」は、我が家にもカミさんが読んだらしく有ります。しかし、私もまだ読んでません。
私も高齢となりボケ老人の部類ですが、2人で暮らして行けるうちはいいのですが、私1人になった場合、子供達に迷惑をかけたくないので老人介護施設へ入ろうと思っています。
たまたま、前職時代の先輩で西区の手稲にこのような施設に入っている人がいるので、近々様子を聞きに行って見ようと思っています。
[ 費用の件で一言 ] 最近新聞広告にあった「敬老園札幌」では、私86歳の場合 ①家賃:841万円、 ②毎月の管理費:13万円
現役時代に、平均の公務員で費用的に何ら心配なかったのですが、徐々に高額になって私が入る時代には、年金で賄えればいいのですが?
5月 12, 2024 @ 10:53:49
老人介護施設の入居費用は、かなりの高額ですね。情報ありがとうございます。
毎月の管理費が13万円とありますが、年金を13万円以上もらっている人は、国民の何%くらいいるのだろう? 人が生きていくには、管理費だけでは済みそうもないので、やはり貯えが必要ですね。
私の知人にも親を有料施設に入れたら、月々かなりの出費になった、と言っていました。入居1年たたずに亡くなったので、冗談とも本音ともとれる表現で「助かった~」と。
私はぎりぎりまで自宅で生活して、最後の最後は病院で——と考えてますが、目論見通りにいきますかどうか・・・