
ロシア・ウクライナ戦争以来、テレビなどのマスコミに出づっぱりの「超人気軍事研究家(東大先端科学技術研究センター准教授)」による、オホーツク海で展開するロシアの極東軍事戦略の分析。
1960年代後半まで、ソ連と米国の海軍力は、両国の「基礎科学力や工業力の差」や「投下できるリソースの差を如実に示し」、圧倒的に米国が優勢だった。(その力関係はソ連がロシアに変わった今も、基本的には変わっていないし、差は開いたかもしれない)
例えば、1960年代の弾道ミサイル搭載原子力潜水艦(SSBN)を比較すると、ソ連の658型SSBNが搭載していたSLBM(潜水艦発射弾道ミサイル)は、射程1200キロの3発だったのに対し、米国のジョージ・ワシントン型SSBNは射程2600キロのSLBMを16発も搭載することができた。
米国など西側による先制核攻撃を恐れたソ連が考え出したのが、自国中枢が消滅しても、確実に報復することができる“抑止”戦略だった。「自分たちが核攻撃で蒸発しても確実に報復が行われるのだから、先制核攻撃の危機が迫っても焦って報復命令を出す必要がなくなり、したがって危機下における安定性が確保される」と考えた。
その考えの下、主役となったのが、長期間の補給なしに深海に潜んでいることが可能な、つまりは敵に居場所が捕捉されづらいSSBNだった。
米国や日本をも含むその同盟国によって、太平洋は米国の内海化され、ロシア海軍の動きは、潜水艦も含めて逐一捕捉されている。そこで、ロシア近海のオホーツク海と北極海のバレンツ海が、西側の眼が届かないSSBNの隠れ家、つまりは要塞となった。それが著者のいうところの「核要塞」ということらしい。
♪
実をいうと私(=ピカテン)はまったくの軍事音痴である。あとがきで著者が自らを「軍事おたく」と表明しているのを反映するように、「大量の略語や軍事用語が溢れ」た、この本をどう評価していいのかわからない。
ロシアの原潜が、オホーツク海内に潜んでいるのなら、太平洋をうろうろされて、米国などと偶発的な衝突でも起こされるより、けっこーなんじゃないか? な~んてことを思ったりもするのは素人の下手な考えだろうか。
以前は、ソ連・ロシアが北海道に攻めてくるかのような北方脅威論なんかをもてはやし、一方でその技術力のお粗末さを嘲笑う。「北朝鮮の挑発」や「中国の海洋進出」を「冠言葉」のようにニュースに付加して中朝ロの脅威を強調するのも、ジャパニーズ・メディアの報道パターン。
南シナ海の紛争地・南沙諸島近くを、あえて通過したことを誇示する、米国原潜を「挑発」と呼ばないのは何故? ひとえに日本が西側に属しているが故なんだろうけど、東側やイスラム世界、「南」の国々からは、まったく逆に見えるかもしれない、とは考えないのだろうか。
♪蛇足
この本の159ページに、カムチャッカなど極東に飛来する、米国からの弾道ミサイルを探知するため、ソ連がハバロフスク州にドッガと呼ばれる、巨大な長距離レーダー施設(超水平線レーダー)を建設した話が出てくる。ドッガの実戦配備型1号機は、ウクライナのチェルノブイリに設置された。
私=ピカテンは2015年に、かのチェルノブイリ原発を見学し、その過程でこの巨大なレーダー施設にも立ち寄った。原発同様、今や巨大な無用の鉄の塊だった。











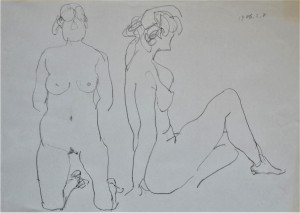





















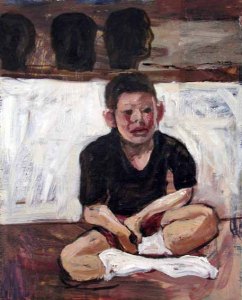


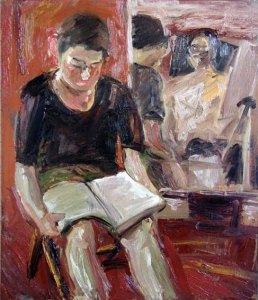



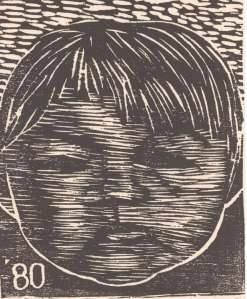


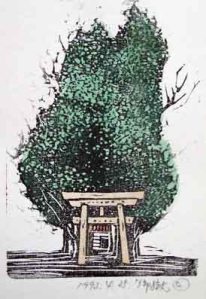









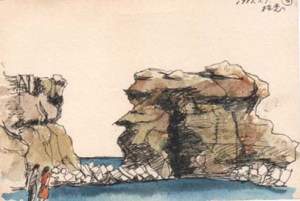






















コメントを残す