著者は20代の終わりから40代のはじめまでの13年間をイタリアで過ごした。そこで出会った、印象深い人々やエピソード、街の風景などをつづった12編のエッセイ。「霧」と「透明」は一見矛盾する表現かもしれないけれど、どの作品にも透明感のある静寂さが満ちている。
ノートに書き写しておきたくなるような文章が、いくつもある。
「この都会(ナポリ)には、秩序とか、勤勉とか、まがりなりにも現代世界に生きると自負する私たちが、毎日の社会生活において遵守しなければならないと自ら信じ、人にも守らせようと躍起になっているもろもろの社会道徳を真っ向から無視して、大声で笑いとばしているようなところがある」(「ナポリを見て死ね」)
タブッキの小説にこんな話があった。「ある本に1枚の写真がのっていて、ひとりの黒人が勢いよく両手をあげて、まるでマラソンのゴールイン寸前のような格好で写っている。ところが、つぎのページでは、その写真が全体の一部分でしかないことが明かされる。全体というのは、南アフリカの黒人弾圧の場面を撮った写真で、勝利の瞬間のように両手をあげた黒人は、たったいま官憲の銃弾に撃たれて、倒れ込む瞬間なのだ」。タイトルは「アンソロジーにはご用心」。「作品全体を把握せずに、部分で用をすませるのは危険だ、タブッキは、彼らしい、なにげない調子でつぶやいている」(同)
「自分があわや騙されかかった相手には、はじめから気にくわない相手に対してよりも、腹が立つものだ」(「鉄道員の家」)
「夫を亡くして現実を直視できなくなっていた私を、睡眠薬をのむよりは、喪失の時間を人間らしく誠実に悲しんで生きるべきだ、と私をつよくいましめたガッティ」(「ガッティの背中」)。十代にしてレジスタンスに参加した経験のあるガッティは、気難しい変りものの編集者だった。その彼がアルツハイマー病で精神病院暮らしとなり、久しぶりに彼を訪ねた著者が目にしたのは、「年齢を跳びこえてしまった」ガッティだった。
切ない、悲しみにも似た情感がこころに残る。 本のタイトルにつながる「遠い霧の匂い」も、最後のエピソードが、いつまでも鮮明な画像のように尾を引く。











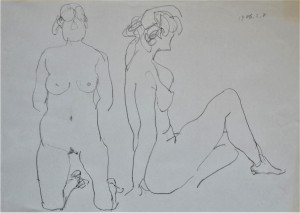





















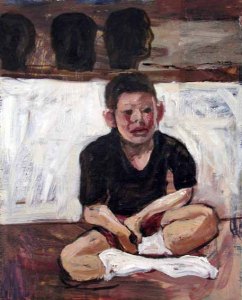


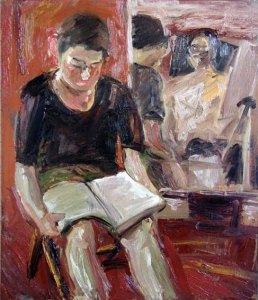



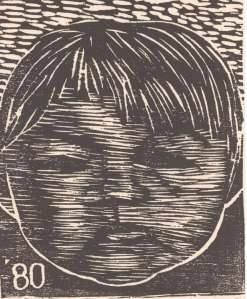


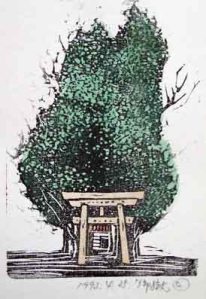









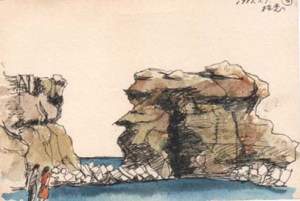






















コメントを残す